| 前ページまでの「本能寺の変・山崎の戦」の研究レポートは御覧いただけたでしょうか。「最初の研究レポートは長いし読むのが面倒そうだから、楽そうな旅行記から読むか」と思って、このページを読んでいる方もいらっしゃるかもしれませんが、まぁいいです。 さて、前ページまでの原稿を読んだ方ならお分かりでしょうが、本能寺の変・山崎の戦の舞台は、現在の行政区分で言うと京都府です。本能寺は京都市内にありますし、山崎の戦が行われたのは、現在の大山崎町というところです。我々歴史研究会は、本能寺の変・山崎の戦が実際にどのような場所で行われたのか、その地理的な感覚をつかむために、今年の春、京都・滋賀(滋賀県には、信長の居城の安土城や光秀の居城の坂本城があります)への調査旅行を実施しました。本稿はその旅行記です。どうか最後までお付き合いください。 |
| 今回の旅行の特色の一つは、歴史の研究とは何の関係もないことなのですが、行き帰りともに夜行列車を利用した、ということです。これによって、二日間、太陽が出ている時間帯を現地で目一杯利用することができるのです。 もっとも、これは新幹線を使うだけのお金がなかっただけの話で、「特色」というほどのものではありませんが。 3月29日の0時26分に大船駅を出る「ムーンライトながら」で、出発した我々は、長時間座っていたことが原因のエコノミークラス症候群を起こしつつ、七時ごろ大垣駅に到着。そこから電車を乗り換えて二隊に分かれ、一方は安土城へ、もう一方は現地の資料を入手するために京都市歴史資料館へと向かいました。私は安土隊に属していたのですが、安土駅から安土城跡へ向かう道に片足を失ったおまわりさん人形(田舎の道によくあるやつ)が立っており、人生の悲哀のようなものを感じさせていました。安土城は山崎の戦の後に焼け落ちてしまったので、石垣しか残っていませんでしたが、城門跡から天守閣跡 まで相当階段を上らなければなりませんでした。
その後、京都隊と京都駅で合流し、光秀の居城である亀岡城跡へと向かいました。ですが、亀岡城跡へ到着したところで大変なことが発覚。亀岡城跡が「大本教」という新興宗教の私有地になっており、入り口のところに「ここから先は聖地だからお祓いを受けていない人は入っちゃいけません」という看板が立っているのです。大本教によれば何十年も前に亀岡城跡を「第二の聖地」として買い取り、整備してきたとのこと。さすがに、新興宗教の「聖地」に無断侵入することには、気後れがしたので、わが歴史研究会は亀岡城跡へ入ることをあきらめたのでした。ちなみに、亀岡駅前のラーメン屋は、スープの味が平板で麺がふやけているのであまりおいしくないです。避けたほうが賢明でしょう。 |
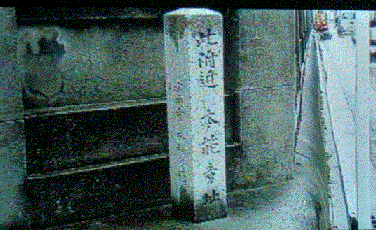 その後、京都市の南を流れる桂川を見に行き、さらに本能寺の跡地(左写真)へと向かいました(この間に雨が降り出しました)。本能寺は本能寺の変のときに焼け落ちてしまっており、今ある本能寺は後世に違う場所に再建されたものです。その本能寺跡地というのは、今は本能小学校(考えてみるとすごい校名だ。本能…)という小学校になっています。 その後、京都市の南を流れる桂川を見に行き、さらに本能寺の跡地(左写真)へと向かいました(この間に雨が降り出しました)。本能寺は本能寺の変のときに焼け落ちてしまっており、今ある本能寺は後世に違う場所に再建されたものです。その本能寺跡地というのは、今は本能小学校(考えてみるとすごい校名だ。本能…)という小学校になっています。ですが、残念ながら本能寺跡地ではなぜか工事をしており、入ることはできませんでした。その後、雨の中を近衛前久邸跡地(駐車場になっていた)や誠仁(さねひと)親王の住んでいた二条邸の跡地へ立ち寄りながら、宿舎の東山ユースホステルへと帰っていきました。
現本能寺の信長廟所 |
 天王山から山崎古戦場を眺める 天王山から山崎古戦場を眺めるその後、京都市外に出て、山崎の戦が行われた古戦場跡へと向かいました。大山崎町歴史資料館というところで資料や地図を入手してから、桂川沿いに秀吉陣の方から古戦場をてくてく歩く。山崎の辺りは天王山が淀川のほうへ大きく張り出した地形をしているので、軍勢も川沿いに布陣せざるをえないのです。川沿い、特に下流に布陣することは、本来兵法では最も戒めるところなのですが…。さらにその後、有名な天王山に上りました。その中腹に、「山崎合戦の碑」という碑が立っていました。元経済企画庁長官の堺屋太一氏が山崎の戦の様子を書いた碑文が付いていましたが、いい加減なものなので信用しないほうがいいでしょう。 下山してから勝竜寺(しょうりゅうじ)城へと向かいます。勝竜寺城は現在は公園になっており、隅っこの鳥かごの中になぜかクジャクが住んでいました。肝心の城郭のほうも改変されており、歴史的な価値はあまりありませんでした。 その後、我々は再び二隊に分かれ、一方は山科へ、一方は京都市内へ戻って本能寺の宝物館を訪ねました。山科隊は、明智光秀が土民に殺されたといわれている(はっきりしたことはよく分かっていません)小栗栖の明智藪というところへ行き、石碑を見てきました。京都隊の方は、本能寺の宝物館に行ったわけですが、展示内容は日蓮上人がどうしたこうしたと、ほとんど法華宗関係のものばかりで(まぁお寺の宝物館なんだから、当然ですが)、本能寺の変関係の展示は、森蘭丸が背負っていたと称する刀やら、本能寺が襲われたときに鳴いて危険を知らせたという蛙の香炉など、怪しげなものしかありませんでした。 これで全行程が終了。我々は京都市内に戻り、夕食をとってから、疲労した体を抱えつつ、夜行列車に乗って帰っていきました。 それにしても、今後は一泊三日などというハードスケジュールはごめんこうむりたいところです(安上がりでいいんだけど、夜行で腰が痛くなるのにはまいりました)。 堺屋太一氏制作の屏風 |
 さて、安土城を一巡りした安土隊は、次に安土城考古博物館というところへ向かいました。この博物館は相当立派な建物と広い駐車場を有し、周囲の畑とは不調和に傲然と突っ立っていました。「国民の税金は果たして的確な使われ方をしているのだろうか」などということを考えつつ、入館しましたが、展示には特筆すべきことはなく、収穫といえば史料集(書状・日記などの古文書の写真を載せた本。歴史研総裁の出川君はこの本を見て大興奮していた。彼の独特の感性は常人には理解しがたい)を入手できたことくらいでした。その後近くにある「信長の館」という変な形をした建物に入りましたが、中には安土城の天守閣を再現したとかいう原寸大模型があるだけでした。「信長の館」を出たとき、このままだと電車の発車時刻に間に合いそうもない、ということに気づき、駅まで1キロ近く走って何とか間に合いました。いや、本当にしんどかった。
さて、安土城を一巡りした安土隊は、次に安土城考古博物館というところへ向かいました。この博物館は相当立派な建物と広い駐車場を有し、周囲の畑とは不調和に傲然と突っ立っていました。「国民の税金は果たして的確な使われ方をしているのだろうか」などということを考えつつ、入館しましたが、展示には特筆すべきことはなく、収穫といえば史料集(書状・日記などの古文書の写真を載せた本。歴史研総裁の出川君はこの本を見て大興奮していた。彼の独特の感性は常人には理解しがたい)を入手できたことくらいでした。その後近くにある「信長の館」という変な形をした建物に入りましたが、中には安土城の天守閣を再現したとかいう原寸大模型があるだけでした。「信長の館」を出たとき、このままだと電車の発車時刻に間に合いそうもない、ということに気づき、駅まで1キロ近く走って何とか間に合いました。いや、本当にしんどかった。 3月30日朝。旅行前の天気予報では80パーセント以上の確率で雨、となっていましたが、日頃の行いが良かったのか(?)、幸運にも天気は晴れていました。朝食後、地下鉄で現本能寺(後世に再建されたもの)へ。信長の廟(びょう)(左下写真)や宝物館などがありましたが、宝物館はまだ開いていなかったので、たいした収穫もなく、後で宝物館が開いたころにまた戻ってくることにして、本能寺を後にしました。
3月30日朝。旅行前の天気予報では80パーセント以上の確率で雨、となっていましたが、日頃の行いが良かったのか(?)、幸運にも天気は晴れていました。朝食後、地下鉄で現本能寺(後世に再建されたもの)へ。信長の廟(びょう)(左下写真)や宝物館などがありましたが、宝物館はまだ開いていなかったので、たいした収穫もなく、後で宝物館が開いたころにまた戻ってくることにして、本能寺を後にしました。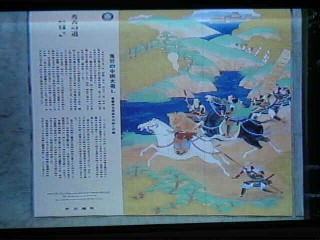 二隊が山科駅で合流してから、今度は湖西線で琵琶湖畔にある光秀の居城坂本城へと向かいました。坂本駅からタクシーで坂本城跡へ。城跡といっても名ばかりで、ほとんど何も残っていないのですが、光秀の石像が立っていました。
二隊が山科駅で合流してから、今度は湖西線で琵琶湖畔にある光秀の居城坂本城へと向かいました。坂本駅からタクシーで坂本城跡へ。城跡といっても名ばかりで、ほとんど何も残っていないのですが、光秀の石像が立っていました。